080416up
「マガジン9条」の発起人の1人でもある小児科医、「たぬき先生」こと毛利子来先生。
お仕事や暮らしの中で感じた諸々、文化のあり方や人間の生き方について、
ちょっぴり辛口に綴るエッセイです。
こども医者毛利子来の『狸穴から』(8)
もうり・たねき(小児科医) 1929年生まれ.岡山医科大学卒業。東京の原宿で小児科医院開業。子どもと親の立場からの社会的な発言・活動も多い。「ワクチントーク全国」元代表、「ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議」元副代表などを経て、現在は雑誌「ちいさい・おおきい・よわい・つよい」編集代表、『マガジン9条』発起人などを務める。著書に『ひとりひとりのお産と育児の本』(1987,毎日出版文化賞)、『赤ちゃんのいる暮らし』、『幼い子のいる暮らし』などがある。最近は、友人でもある小児科医・山田真氏との共著である『育育児典』(岩波書店)が、評判を読んでいる。HP「たぬき先生のお部屋」
木を見て森を見ず
子どもの診療をしていて、いつも苛立ちを感じることがある。
なに、子どもが動き回ったり泣き叫ぶことなどではない。そんなのは、ひとつも苦にならない。むしろ、賑やかに遊ばれると、楽しくなる。泣き叫ばれたら、ああ、元気があるな、重い病気ではないなと安心する。
だいいち、無遠慮に遊ぶのは、ぼくを友達くらいに思ってくれている証拠。子ども医者としては冥利に尽きる。診察のときに暴れるのも、しつけが悪いわけではない。イヤなことに全力で抵抗するのは、素敵でさえある。
だから、ぼくが苛立ちを感じるのは、そんな子どもに対してではない。
そうではなくて、子どもを連れてくる親たちに対してなのだ。
その最たる例が、以下のようなこと。
ほとんどの親が、診察室に入ってくるなり、息せき切っていう。
「夕べは37度5分だったんですが、今朝は39度になりました」といった調子。
きっと、何回も何回も、体温を測ってきたにちがいない。
だが、体温と病気の重さとは、かならずしも、比例しない。熱が高いから病気が重いとか、熱が低いから病気は軽いとはかぎらないのだ。
実際、40度もあるのに走り回っている子どもがいる。そんな子は、病気が重いはずはない。少なくとも、急を要する事態ではなかろう。逆に、37度ちょっとしかないのに、ぐったりしている子がいる。そんな子は、軽いとはいいにくい。少なくとも、見くびってはならぬだろう。
だから、病気の軽重と緊急度は、熱の高さよりも、元気と機嫌のぐあいで判断するほうが、よほど気が利いている。
それに、そもそも、体温計にばかり頼るのはどんなものか。
どうやら、数字で示されるから科学的と信じられているようだが、実は、さほど科学的ではない。
なにしろ、体温は、全身で一様ではない。暖かい所と冷たい所があるはずだ。
それに、体温は、時々刻々変化してやまない。特に子どもは急に熱くなったり冷たくなったりする。
なのに、体温計は、それをはさんだ場所の、その時の温度が知れるだけなのだ。
だから、熱の程度を知りたければ、体温計よりも、子どもが発する熱を全身から感じ取ることのほうが、ずっと気が利いている。
たとえば、抱いたときに立ち上る熱さ。吐く息にふっと漂う熱さ。
そして、そんな感じは、常日頃から子どもの面倒をみている人でこそ、敏感にとらえられるにちがいない。
ところがだ。このごろは、そうした直感が軽んじられすぎている。子どもが全身で物語る様子も無視されている。そして、体温計が示す数字ばかりが信用されている。
そういえば、入院している子が「息が苦しい」と訴えているのに、やってきた看護師が指先で酸素濃度だけ測って「正常値だから大丈夫」と、なんの看病もせずに行ってしまったという話を聞いたことまである。
「木を見て森を見ず」という諺があるが、今の医療は、まさにそうなっている。
ということは「病気を治そうとして人間を殺す」医療になりはてているのだ。
最近の「後期高齢者医療制度」などを見ても、その感を深くする。
まさに本末転倒。医療以外の制度や行政まで、そうなっていなければいいのだが。
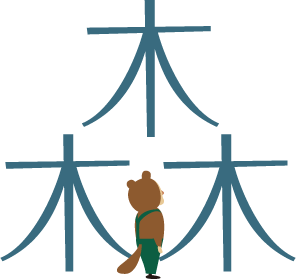
現実は、果たして…?
皆さんのご意見をお待ちしています。