マガ9スポーツコラム No.005
090617up
みんなが大好きなスポーツ!「マガ9」スタッフだってそうです。
だから時々、メディアで報じられているスポーツネタのあれこれに、
突っ込みを入れたくなったり、持論を展開したくなったり・・・。
ということで、「マガ9スポーツコラム」がスタートです。不定期連載でお届けします。
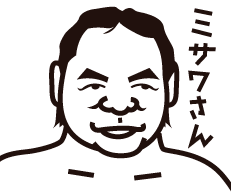
追悼・プロレスラー三沢光晴さん
6月13日、プロレスラーの三沢光晴さんが亡くなった。広島県立体育館での試合中、相手選手のバックドロップを受けた後、マット上で動かなくなったという。死因は頸髄損傷だった。
三沢さんは故ジャイアント馬場選手のDNAを最も受け継いだプロレスラーだったと私は思っている。馬場さんは2メートルを越える大型レスラー。長いリーチから相手の頭に振り下ろす脳天唐竹割り、相手の顔面を覆い隠してしまうほどの大きな足での16文キックが代名詞。一方の三沢さんは身長185センチで、トップロープからのダイビングボディプレスなど、抜群の運動神経を駆使した技を得意としていたから、「レスリングスタイルがまったく異なるのに」といぶかる向きがあるかもしれない。だが、2人はリング上では寡黙で、かつ徹底して「受身」を重視したレスラーだったのである。
受身はすべての格闘技の基本であり、プロレスラーの専売特許ではない。ただ、たとえば柔道のそれと違うのは、プロレスラーの受身が、相手の技にきちんと「かけられる」ことも目的であることだ。プロレス技の凄みは、やられる側が体現するのである。
プロレスの歴史を遡れば、街頭テレビで日本人を熱狂させた力道山が思い浮かぶだろう。力道山がルー・テーズやシャープ兄弟、デストロイヤーといったアメリカのレスラーを倒す姿をみて、敗戦に打ちひしがれていた日本人は溜飲を下げた(力道山自身は現在の北朝鮮出身であるが)。
力道山の死後、ジャイアント馬場(全日本プロレス)とアントニオ猪木(新日本プロレス)がプロレス界の中心になると、日本人=ベビーフェースvs外国人選手=ヒールという構図が、高度成長期を終えて、日本経済が欧米にキャッチアップする時代とともに変化していく。全日本プロレスは、多くの外国人選手を招聘し、彼らの華やかな戦いを中心に置いた。新日本プロレスは、アントニオ猪木vsモハメド・アリに象徴される異種格闘技路線に向かった。そしてバブル期には、日本人レスラーの軍団抗争がメインとなるが、バブルがはじけた後、馬場さんはこれまでの派手さやストーリー性を廃し、リング上での激しい攻防に純化したものを目指していった。
そうした路線の中心にいたのが三沢さんだった。遺恨などリング外の話題は抜きに、ファイトだけで観客をひきつける。並大抵のことではない。相撲や柔道、あるいは総合格闘技でも勝敗が重視されるのに対して、プロレスの観客は選手がどんな技をかけあうか、その過程に注目するからである。
いかに相手のよさを引き出しながら、最後には勝つか。「観客」と「勝負」の両方を意識したパフォーマンス。プロレス会場に、ボクシングの試合が漂わせるような殺伐さや悲壮感がないのは、プロセスを重視するオタッキーなファンが多いからでもある。
1999年1月に馬場さんが亡くなってから約1年半後、三沢さんは全日本プロレスを辞めて、興業会社「プロレスリングノア」を立ち上げた。それ以降、社長兼選手として日々、奮闘を続けたが、近年は観客動員数が伸び悩み、経済危機の影響もあって、日曜深夜枠の地上波テレビ中継も2009年3月で打ち切られた。スポンサー探しなど、経営者として心身にストレスを蓄積させていたのだろう。でなければ、受身の天才がバックドロップを受け損ねて亡くなるとは考えられない。
三沢さんは馬場さん同様、リングでのマイクパフォーマンスなど、派手なことを好まない人だった。いまから10年ほど前、小橋健太選手とのタイトルマッチで、フィニッシュのエルボーバットを放つ直前、珍しく「うわー」と雄叫びを上げたことがある。
「嫌いでもない相手を思い切り殴る。そんなの本当はいやじゃないですか。でも、やらなきゃ勝てない。自分のなかのためらいを振り払うため、声を出さざるをえなかったんです」
試合後にこんなコメントを残すプロレスラーを、私は彼以外に知らない。
三沢光晴さん、享年四十六才。合掌。
(芳地隆之)
ご意見募集