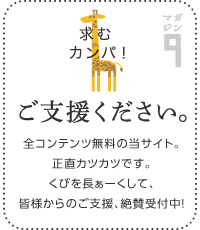憲法と社会問題を考えるオピニオンウェブマガジン。
|「マガジン9」トップページへ|時々お散歩日記:バックナンバーへ|
2012-03-07up
時々お散歩日記(鈴木耕)
84映画『原子力戦争』と「東大話法」
ある原子力発電所の事故の資料を入手した新聞記者が、事故処理の指導のために東京からやって来た偉い原子力の学者先生に、その資料を示しながら、事故についてインタビューする。
記者「たとえば冷却水が漏れて、それで炉内が空焚き状態になるとか、燃料棒が欠損して、何かチャイナアクシデントにつながるような…」
学者「ちょっと待って下さい。私は、そのチャイナアクシデントという言葉をそう簡単に使ってもらいたくないんだな。
あなた方が原子炉の安全ということに神経を尖らせていることはよく分かります。私だって、安全な原子炉ということについては人後に落ちないつもりだ。でも、現実の問題として、チャイナアクシデントという現象はそうむやみに起こるものではない。たとえ、今あなたが言ったような事故があったとしても、それが原子炉の圧力容器を破壊するまでには、いろんな安全装置が組み込まれていて、チャイナアクシデントが起きるには、それらの装置がすべて正常に動かない、最悪のファクターが全部重なったときのみに限る。それは、家1軒が火災になったからといって、その火が東京中に燃え広がるとは考えられない程度の可能性と言っていいかもしれない。
このごろでは、原子力発電所で事故があると、その内容が何であれ、すぐチャイナアクシデントだと短絡される。これじゃかえって原子炉の怖さを見誤ることになりはしないかと心配です」
記者「しかし、その可能性はあるでしょう」
学者「その可能性があるとすれば、今、私と話しているあなた自身に、空から落ちてきた隕石が当たって死ぬ、という可能性もあるんです」
(中略)
記者「この資料は本物ではないと?」
学者「私の立場として言えることは、これは絶対に本物ではありえない、ということです。もし仮に、原子力発電所で、今あなたが指摘しているような、チャイナアクシデントにつながるような、燃料棒の欠損溶融事故が起こって、その事故が公表されたら、日本で今進められている原子力発電所の開発計画はメチャクチャになってしまう。
そんな危険な資料を新聞記者のあなたが入手できるわけがない。その写真を持っているということが、それが本物でないことの何よりの証拠だ」
記者「でも、事実を隠してしまうのはよくないと思うんです。事実を伝えるのが、私たちの役目です」
学者「今、あなたは目先のことだけを追いすぎている。原子力発電所はまだ端緒についたばかりで欠陥も多い。だがそれを乗り越えて、より完全な原子力発電所を造らなければならない使命を、私たちは担っている。放っておけば誰かがやってくれるというものでもない。私たち自身がそれをやらなければならないんだ」
記者「危険を冒してでもですか」
学者「やむをえない」
記者「そりゃ、危険だ」
学者「そう、確かに危険もある。だが、私たちが今、もっとも頼りにしている石油資源も、いつ手の届かないものになってしまうかも分からない。
今もし、アラビア湾が封鎖されでもしたら、どうなると思う? それが仮に6ヵ月続くと、中東から日本に石油が入ってこない期間は航行日数も入れて7ヵ月から約8ヵ月近くになりますね。日本は石油の輸入を81%中東に頼っている。ですから、石油の輸入は平常の20%になり、それが200日間続くと日本中で300万人が死に、財産の70%が失われることになります。
実に日本人の約半数が死線をさまようわけです。しかも、そのアラビア湾の封鎖の確率はきわめて高いのです。私たちはそんな危なっかしいものを命綱として生きているんです。これほどの危険がほかにありますか。私たちは、エネルギー源としてはできるだけ多くのものを持っていなければならない。石炭でも石油でも原子力でも…」
つい最近の現実の取材のメモ、と言われてもそのまま通りそうなやりとりである。しかしこれは、1978年に公開された映画『原子力戦争』での一場面だ。原作は田原総一朗(1976年)で、黒木和雄監督、原田芳雄(ヤクザ)、佐藤慶(新聞記者)、岡田英次(学者)らの出演。
上記の部分は、佐藤慶の取材に対する岡田英次の受け答えを、僕が映画を観ながらメモしたものだ。したがって、言葉遣いに多少の違いがあるかもしれないが、内容はほとんど間違いない。
なお、僕は最近の田原総一朗氏はまったく評価しないが、この小説だけは素晴らしいと思っている。現在はちくま文庫に収録されている。
それにしても、この学者先生の物言いは、最近までの、特に東大系の原子力学者たちにそっくりではないか。この映画が作られたのは、今から34年前だ。彼ら原子力ムラの住人である学者たちの「話法」は、数十年間変わっていない。いや、むしろもっと威丈高に素人である我々を威圧する「話法」に変化してきた、といっていい。
映画では、事故の事実に迫った新聞記者は、結局、電力会社とつるんだ新聞社本社幹部の指令により、特ダネを握りつぶされる。それも、つい最近までの原発報道によく見られたパターンだ。
最近、『原発危機と「東大話法」』(安冨歩、明石書店、1600円+税)という本を読んだ。学者たち、特に東大系の原子力学者たちがどのような話し方をするかを、自らも東大教授である著者が分析した本だ。これがめっぽう面白い。中でも原発に関しては「原発話法」とでも言うべき特殊な原子力ムラ特有の「お家芸」があるらしい。
映画『原子力戦争』の中の学者先生の物言いが、この本の分析にあまりにピタリと当てはまることに、僕は呆れながら驚いたのだ。数十年にわたって磨きぬかれた「東大話法」が、この国の原子力政策をここまで歪めてきたということが、ほんとうによく分かる。
「東大話法規則一覧」という表が、この本に載っている。それは20項目に及ぶ。さまざまな規則があるが、先の映画の学者の物言いにあてはめてみる。
規則3 都合の悪いことは無視し、都合のいいことだけ返事をする。
規則4 都合のよいことがない場合には、関係のない話をしてお茶を濁す。
規則5 どんなにいい加減でつじつまの合わないことでも自信満々で話す。
規則11 相手の知識が自分より低いと見たら、なりふり構わず、自信満々で難しそうな概念を持ち出す。
規則13 自分の立場に沿って、都合のよい話を集める。
規則14 羊頭狗肉。
規則16 わけのわからない理屈を使って相手をケムに巻き、自分の主張を正当化する。
規則17 ああでもない、こうでもない、と自分がいろいろ知っていることを並べて、賢いところを見せる。
規則18 ああでもない、こうでもない、と引っ張っておいて、自分の言いたいところに突然落とす。
映画の中の、あの短い記者とのやり取りの中で、学者はこれだけの規則にのっとった「東大話法」を駆使していた。ひとつひとつ見ていけば、よく分かる。
絶対安全神話を「安全装置がすべて壊れる最悪のファクター」でごまかす。都合の悪い部分には言及しない。
一軒の家の火災と東京中の炎上、原子炉事故と隕石落下による事故を比べる。自分の知識をひけらかして、素人は口を出すなと言わんばかりに資料を否定する。特にこの「隕石に当たる可能性」というヘリクツは、今回の原発事故についてのテレビ番組でも、偉そうな先生たちが繰り返すのを何度も耳にした。あれは、こんな昔から使われていたたとえ話なのか。もう「にっぽん昔話」の領域である。
「この資料は本物ではないのか」と問われて、ほとんど答えにならない答えで記者を一喝する。どう考えてもまともには答えていないのだが、話の流れで誤魔化してしまう。
突然、アラビア湾の事態を持ち出して原発の必要性を説く。さらに、それによって日本人の半数が死線をさまようという妙な数字で、記者の質問をはぐらかし、自分の主張を正当化する。まさに「自分の立場に沿って、都合のいい話を集め」て、記者をケムに巻くのだ。
細部の数字を持ち合わせていない記者は、その立て板に水のような学者のヘリクツに圧倒される。記者が「事実を隠すのはよくない」と問いかけても「目先のことばかり追いかけるな。我々は使命を担ってやっているのだ」と、いつの間にか自分たちは国家の命運を背負う高みに昇って、他の人間たちを見下ろすのだ。
実に、これがこの国の原子力政策を担ってきた連中のやり方だったのだ。そんな連中の推進だったのから、日本の原発が爆発してしまったのは、残念ながら、やはり必然だったと言うしかない。
決して「原発」とは言わず「原子力発電所」とフルで話すのは、原発事故の初期のころ、しきりにテレビで「原発の安全性」を強調していた関村直人東大大学院教授などにも見られた。彼らはそれだけ「原子力発電所」に強い思いを抱いていたのだろうが、そこには「原発などと略称で話す輩は素人だ」という思い上がりがあったのではないか。
しかし、そんな原子力専門家たちは、事故に際して何ひとつ有効な手を打てなかった。あの班目春樹原子力安全委員会委員長(彼も典型的な東大系原子力学者)は、原発が爆発したと聞かされて「はーっ」と言って頭を抱え一言も発することができなかった(朝日新聞「プロメテウスの罠」、単行本『プロメテウスの罠』は学研刊)という。いったいどこが「専門家」だったのか。
いずれにせよ、このような学者たちの助言を基に、日本の原子力政策は行われてきたのだ。それが間違いだったということは、何よりも原発周辺から追い出された被災者たちの苦労が物語っている。周辺のみならず、日本全国へ拡がった放射能汚染の実態が、原発というものの、あらゆる生物、ことに人間との「非共存性」を示しているではないか。
だが、野田首相は見て見ぬ振りをする。彼の「再稼働」への執着は尋常ではない。どれだけの鼻薬を、財界と称する老醜たちに嗅がされればそうなるのか。
やや古い記事(東京新聞2月25日付)だが、野田首相はこんなことを言っている。
原発再稼働 規制庁発足前に判断も
野田佳彦首相は二十四日、本紙のインタビューに応じ、定期検査中の原発の再稼働について「原子力規制庁ができる前に判断することもあるかもしれない」と述べ、四月予定の規制庁発足前に結論を出す可能性に言及した。国の原子力安全委員会が現在、関西電力大飯原発3、4号機の安全評価(ストレステスト)の一次評価を審査しており、同原発の再稼働を年頭においた発言とみられる。
すると今度は、それに呼応するような出来事も起きてくる(東京新聞3月4日付)。
伊方3号機も妥当方針
保安院、安全一次評価、3基目
四国電力伊方原発3号機(愛媛県、定期検査で停止中)の再稼働の前提となる安全評価(ストレステスト)の一次評価について、経済産業省原子力安全・保安院は三日までに、同電力が提出した評価結果を妥当と判断する方針を固めた。
早ければ九日にも専門家会議に素案を示す。保安院の判断は、関西電力大飯3、4号機(福井県)に次ぎ三基目。(略)
僕はこの「原子力安全・保安院」という名前を聞くだけでモーレツに腹が立つ。何が、安全か、保安か!
だが僕の怒りはさておいて、明らかにこれは、野田首相の再稼働方針に呼応した経産省と電力会社の共同作戦・デキレースだ。いかに新設官庁とはいえ、発足直後に「原発再稼働」を言い出せば「どこが原子力規制庁か、保安院と何も変わらないではないか」との批判を受けるのは確実だろう。これからの原子力行政に最初から疑問を持たれることになる。さすがに、それだけは避けたい。だから規制庁発足前に、とにかく「再稼働」だけは決めておきたい。姑息なやり方だ。
学者の世界に「東大話法」が蔓延しているとするならば、政治家の世界にはどんな「話法」があるのだろう?
こんな連中が牛耳る社会。残念ながら、暗い未来しか見えてこない。
ふるさと秋田にしばらく帰ってきた。あの大震災のちょうど1週間前に亡くなった我が老母の一周忌。家族だけの小さな法事。それを見守るように、雪が降りしきっていた。
雪に埋もれた墓までは、とても行き着けない。冷え冷えとした寺の本堂に、香の薄青い煙と和尚さんの朗々たる読経の声だけが流れていた。外はなお、圧倒的な雪の中…。
しかし、啓蟄も過ぎた。この冬はほんとうに寒かったけれど、もうじき虫たちは目を覚まし、花も開き始めるだろう。だが、なんとしてでも原発だけは再び目覚めさせてはならない。

鈴木耕さんプロフィール
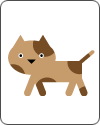 すずき こう1945年、秋田県生まれ。早稲田大学文学部文芸科卒業後、集英社に入社。「月刊明星」「月刊PLAYBOY」を経て、「週刊プレイボーイ」「集英社文庫」「イミダス」などの編集長。1999年「集英社新書」の創刊に参加、新書編集部長を最後に退社、フリー編集者・ライターに。著書に『スクール・クライシス 少年Xたちの反乱』(角川文庫)、『目覚めたら、戦争』(コモンズ)、『沖縄へ 歩く、訊く、創る』(リベルタ出版)など。マガジン9では「お散歩日記」を連載中。ツイッター@kou_1970でも日々発信中。
すずき こう1945年、秋田県生まれ。早稲田大学文学部文芸科卒業後、集英社に入社。「月刊明星」「月刊PLAYBOY」を経て、「週刊プレイボーイ」「集英社文庫」「イミダス」などの編集長。1999年「集英社新書」の創刊に参加、新書編集部長を最後に退社、フリー編集者・ライターに。著書に『スクール・クライシス 少年Xたちの反乱』(角川文庫)、『目覚めたら、戦争』(コモンズ)、『沖縄へ 歩く、訊く、創る』(リベルタ出版)など。マガジン9では「お散歩日記」を連載中。ツイッター@kou_1970でも日々発信中。
「時々お散歩日記」最新10title
「マガ9」コンテンツ
- 立憲政治の道しるべ/南部義典
- おしどりマコ・ケンの「脱ってみる?」
- 川口創弁護士の「憲法はこう使え!」
- 中島岳志の「希望は商店街!」
- 伊藤真の「けんぽう手習い塾」リターンズ
- B級記者、どん・わんたろう
- 伊勢崎賢治の平和構築ゼミ
- 雨宮処凛がゆく!
- 松本哉の「のびのび大作戦」
- 鈴木邦男の「愛国問答」
- 柴田鉄治のメディア時評
- 岡留安則の『癒しの島・沖縄の深層』
- 畠山理仁の「永田町記者会見日記」
- 時々お散歩日記
- キム・ソンハの「パンにハムをはさむニダ」
- kanataの「コスタリカ通信」
- 森永卓郎の戦争と平和講座
- 40歳からの機動戦士ガンダム
- 「沖縄」に訊く
- この人に聞きたい
- ぼくらのリアル★ピース
- マガ9対談
- 世界から見たニッポン
- マガ9スポーツコラム
- マガ9レビュー
- みんなのレポート
- みんなのこえ
- マガ9アーカイブス