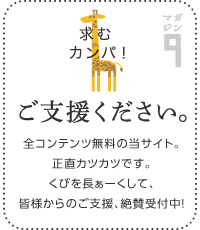マガジン9
憲法と社会問題を考えるオピニオンウェブマガジン。
|「マガジン9」トップページへ|時々お散歩日記:バックナンバーへ|
2011-03-16up
時々お散歩日記(鈴木耕)
38もし、原発が…
どう言っていいか分からない。 言葉がうまく出てこない。
僕の実家は秋田。弟の一家は仙台。あせった。何度電話しても、つながらない。こんなときに、むやみに電話してはいけない、とは思った。しかし、家族の安否は、どうしても確認したい。
やっと通じた。仙台の弟宅はかなりの損傷を受けたらしいが、家族はみんな無事だという。秋田は、目立った被害なし。ようやく安堵した。それが11日。
しかし、安堵の胸はざわめき返す。11日夜から12日、被害は想像を絶する規模に。我が家族のことはさておいて、悲惨な報道に吐き気さえ感じる。そして、原発。恐ろしい、切ない、怖い…。いや、言葉にできない感覚。胃がジリジリと呻いている。
実は、地震のほんの1週間前、僕は故郷にいた。兄も姉も弟も、みんな実家に集まっていた。母が3月4日に亡くなったからだ。とりあえず、兄姉弟の4人、母の死に目には間に合った。それだけでも、せめてもの慰め。ほとんど兄弟だけで、ささやかな葬儀をした。
もし母の死が数日遅ければ、僕ら兄弟は秋田に釘付け、自宅に戻ることもできなかっただろう。もし11日以降の死だったら、死に目には会えなかった。母の、最後の心配りだったか…。
秋田は寒く、まだ雪の中だった。
兄は埼玉、弟は仙台、僕は東京。それぞれが自宅に戻って、ようやく心も落ち着いたころ、凄まじい大地と海の咆哮。
災害地の福島も仙台も岩手も、東北育ちの僕にとっては親しい土地だ。帰郷するときにはよく車を使う。だから、いろいろな土地に寄り道をする。見憶えのある町や村が、濁流に押し流される映像。辛くて、切なくて、胸がキリキリと痛い。
僕は長い間、雑誌の編集部にいた。
チェルノブイリ原発事故が起きたときは、青年向け総合雑誌編集部にいた。そのころ、僕のふたりの娘はまだ幼かった。僕は“馬鹿”がつくほどの子煩悩だった。だから、あの原発事故が幼な子たちに影響を及ぼさないかどうか、本気で心配した。
原発を調べ始めた。スリーマイル島原発事故についても、雑誌を編集しながら学んだ。広瀬隆さんや高木仁三郎さんと知り合って、いろいろと教わったのは、この時期だ。
雑誌で何度も「原発特集」を組んだ。表現をめぐって、副編集長と怒鳴りあったこともある。やがて、僕は若者向けの週刊誌に移動した。ここでも、懲りもせず「原発特集」を組んだ。異動先で、僕は一応、自分でテーマを決められる立場になっていた。職権を振り回して原発にこだわった。
原子力発電所は、やはり恐ろしい、と僕は思う。
プロメテウスの火。
原子力という自然の摂理に反した力を、人間の手で制御できると思うのは、“思い上がり”ではないだろうか。僕はずっとそう思い続けてきた。危ない、と言い続けてきた。
原発立地は必ず過疎地だ。最初は、どの地域でも反対運動が起きる。恐ろしげなものの隣には住みたくない。誰だってそう思う。しかしその思いは、電力会社が湯水のように注ぎ込む金の前で、やがてもろくも崩れていく。残るのは、賛成派と反対派の抜き差しならぬ反感。地域社会は分断され、崩壊する。
しかも、1基建設されると、同じ地域に2号機、3号機…と、たくさん建設される。今回の福島原発など、第1、第2を併せて10基もの原発が建てられた。ひとつ建設されれば、反対運動はほとんど収束してしまう。諦めだ。だから他地域に建設するよりも、同じ地域のほうが、反対運動を気にせずに建設できる。
こうして、同一地域に原発が林立する。
あるジャーナリスト養成学校の学生たちを動員して、原発の周辺での健康被害調査をしたことがある。週刊誌時代のことだ。
ノンフィクションライターのAさんと、編集部のIくんが指揮をとった。学生たちは現地に泊まりこんで、しかも住民の冷たい目に晒されながら、それでも懸命に調査した。
結果として、原発周辺の住民には、有意の“悪性リンパ腫”の高い発生率が認められた。それを、4週にわたって連載した。
反響は大きかった。そして猛烈な反発を食らった。当該県の知事さんは我が週刊誌を振りかざして、県議会で「こんな三流エロ雑誌の記事などデタラメだ」と叫んだという。当然、当該県、電力会社、日本原電、政府機関などから「抗議文」の洗礼を受けた。その数8通。
「10通になったら、ハワイ旅行御招待かな」などと、冗談に紛らわしながら僕らは記事を続けた。
むろん、裁判も覚悟した。だがなぜか、県も電力会社も政府も、僕らを訴えては来なかった。データを用意し、専門家や研究者たちに話を聞き、弁護士にも相談して待っていたのだが、裁判沙汰にはならなかった。なぜだか、その理由はいまもって分からない。
「記事の内容が間違っていると主張するなら、そちら側でも新たな疫学調査をして、そのふたつのデータをつき合わせて議論しましょう」と、僕らは抗議文へ回答したのだが、県も電力会社も政府も、原発周辺住民の詳しい疫学調査(健康被害調査)は行わなかった。僕らよりも大がかりな疫学調査をしていたら、どんな結果が出ていただろうか。
不思議なのだ。
原発の周辺住民に対する疫学調査は、日本ではまだ正式に実施されたことがない。きちんと調査して、「原発からの影響による健康被害などない」ということを、なぜ政府や電力会社は主張しなかったのか。
それ以降も、僕らの週刊誌は「原発問題」を書き続けたが、電力会社も原子力行政機関も無視を決め込んだ。相手にしなければ、批判もそのうち消えるだろう、と思ったのか。僕らが放った批判の飛礫は、闇に中に吸い込まれるばかりだった。
「どんなに激しい揺れにも耐えられる設計になっている」
「活断層はきちんと把握し、それを避けて立地している」
「強固な岩盤を選んで建設している」
「多重防護の思想が貫徹されている日本の原発に、“もしも”という仮定は必要ない」
「メルトダウンなどあり得ない」
だいたいが、こんな回答。どんなに批判しても、まともに答えてもらったことはない。やっと入手した資料は、黒々と肝心なデータ部分が墨塗りされていたりした。
あってはならないことだけれど、たった1回の強烈な地震が襲えば、それらの「答え」は吹っ飛ぶ。そうなるまで、僕らがどんなに批判しても、電力会社も行政も聞く耳を持たないのか。僕は無力感の中で、そう思っていた。そうならないことを願いつつ。
そして、その悲劇的な「答え」が、ついに示された。
「応力腐食割れ」だの「緊急停止装置」、「非常用炉心冷却装置=ECCS」、「耐震設計指針」、「炉心溶融=メルトダウン」、「MOX燃料」、「プルサーマル発電」などなど、僕もさまざまな言葉を覚えた。
それらの言葉がまるで安全を保証するかのように、学者や電力会社の人たちの口からこぼれる。反対をしていた人たちも、言葉の魔力に魅せられたように、難解な言葉の前に沈黙していく。
「ほんとうに安全だと言い張るなら、もっとも電気を使用する東京に原発を造ればいいじゃないか」
広瀬隆さんは、唇をかみしめながらそう訴えた。
<東京に原発を>
反原発運動のスローガンのように、この言葉は受け止められた。そして、チェルノブイリ原発事故を背景に、日本の反原発運動は高揚した。だが、やはり電力会社も原子力行政組織も、耳を傾けなかった。
もしあのとき、原発を止めておくことができていたなら…。“もし”が虚しいと知ってはいても、そう思わずにはいられない。
原発がメルトダウンを起しているのは確実だ。
「放射能洩れは微量」「レントゲン検査程度にも及ばない量」「体を洗い衣服を替えれば心配ない」…。
むろん、パニックを起さないように、抑えた情報で人心を鎮めようとしているのは理解する。だが、それによって被曝量が増加したらどうするのか。正確な情報を、少しでも早く提供すべきだと思う。
計画停電。
原発停止により電力の供給量が絶対的に不足したために、東京電力管内では、5区域に分けて計画停電を実施し始めた。このため、電車は運休や間引き運転。都市機能はほとんど麻痺状態。
街のスーパーやコンビニから、商品が消え始めている。人々は不安を抑え切れない。
「やはり原発は必要。安全性を再確認して、もういちど原発の復活を。そうでなければ日本のエネルギーは賄えない。産業は停滞し、日本は没落する。それでもいいのか」
出てくるだろうと思った論調が、ささやかれ始めている。
だが、考えて欲しい。
我々日本国民は、いつ原発建設を認めたのか。これほど多くの原発を、日本中の海岸沿いに建設することを、僕らはいったいいつ認めたというのか。
気がついたら、日本の発電量の約3割は原子力発電だった。いつの間にか、原発が主要発電になっていたのだ。国民に是非を問うことなく、国と電力会社は電力の3割を原発に依存した。国家のエネルギー政策の大転換が、国民にその是非を問うことなく行われたのだ。
「原発に賛成か反対か」という国民投票など行われたことはない。国民が投票で認めてしまっていたのなら、いまさら何もいうことはない。しかし、勝手に(!)電力の原発依存量を3割まで増やしておいて、「これだけの電力を止めてしまえば、明日から石器時代に戻らざるを得ない。それでも承知か」と脅しにかかる。
だが実は、原発を恒常的に運転するために、多くの火力発電所を停止状態にしていることを、ほとんどの人は知らない。
いったい誰の了解を取って、これほどまで原発を増やしたのか。この島国の地震多発国で。少なくとも僕は、原発建設を国や電力会社に認めた覚えはない。
少しは反対派の論理にも耳を傾けて、原発を抑制し、自然エネルギーや火力、水力のバランスを考えたエネルギー政策をとっていれば…。虚しい後付けとは思いながら、そう言いたくなる。
この国の政策実行者の悪しき伝統といえるのかもしれない。造っておいて、「あるのだから仕方ない。いまさら他に転換はできない」と開き直る。
「いまは、原発の是非を論じたり、責任を追及したりするときではない。とにかく一刻も早い復旧を」という意見が、ネットなどで流れている。それに異を唱えるつもりはない。だが、ほんとうにそれでいいのか。
原発を復旧させてはならない。責任の所在をうやむやにしてはならない。歴史は繰り返すのだ。時間が経って、また同じことが起きないと誰が言えるか。
きちんと、落とし前だけはつけておかなければならない。2度と悲劇を繰り返さないために。
僕は“もし”を、繰り返してしまう。
もし、原発さえなければ、被災者たちの救援活動はもっとスムーズに行われただろう。救援チームもボランティアも、放射能をケアしながら活動しなければならない。どうしても、風向きや距離を考えての活動になってしまう。活動は鈍る。政府の対策本部も、その議論の大半を、いまや原発対策に割かざるを得ない。被災者救援は遅れるばかりだ。そのために、救えるはずの命が、どれほど失われただろう。
もし、原発がなかったら…。
虚しいとは知りながら、そう言ってしまう。
テレビでほんの一瞬見た映像が、頭から離れない。
被災地の瓦礫の間を、1匹の大型犬が、泥まみれになり濡れそぼりながら彷徨っていた。呆然と歩く被災者のそばへ、くんくんと鼻を鳴らしながら近寄っていく。必死に飼い主を探しているのだろう。ブルブル震えていた。寒さと恐ろしさと、飼い主にはぐれた切なさが、震える背中から伝わってきた。
僕は正視できなかった。涙で、画面がぼやけた。
連日、悪夢を見ている。なんだかよく分からない夢なのだが、この寒さの中で、僕は冷たい寝汗をかいている。そして、おおっ、あうぅっ、などと叫んでいるようだ。隣の部屋で寝ているカミさんが跳ね起きたという。それほど大きな声らしい。
悪夢が、現実にならないように祈ってはいるのだが。
どうにも、眠るのが辛い。
鈴木耕さんプロフィール
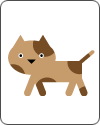 すずき こう1945年、秋田県生まれ。早稲田大学文学部文芸科卒業後、集英社に入社。「月刊明星」「月刊PLAYBOY」を経て、「週刊プレイボーイ」「集英社文庫」「イミダス」などの編集長。1999年「集英社新書」の創刊に参加、新書編集部長を最後に退社、フリー編集者・ライターに。著書に『スクール・クライシス 少年Xたちの反乱』(角川文庫)、『目覚めたら、戦争』(コモンズ)、『沖縄へ 歩く、訊く、創る』(リベルタ出版)など。マガジン9では「お散歩日記」を連載中。ツイッター@kou_1970でも日々発信中。
すずき こう1945年、秋田県生まれ。早稲田大学文学部文芸科卒業後、集英社に入社。「月刊明星」「月刊PLAYBOY」を経て、「週刊プレイボーイ」「集英社文庫」「イミダス」などの編集長。1999年「集英社新書」の創刊に参加、新書編集部長を最後に退社、フリー編集者・ライターに。著書に『スクール・クライシス 少年Xたちの反乱』(角川文庫)、『目覚めたら、戦争』(コモンズ)、『沖縄へ 歩く、訊く、創る』(リベルタ出版)など。マガジン9では「お散歩日記」を連載中。ツイッター@kou_1970でも日々発信中。
「時々お散歩日記」最新10title
「マガ9」コンテンツ
- 立憲政治の道しるべ/南部義典
- おしどりマコ・ケンの「脱ってみる?」
- 川口創弁護士の「憲法はこう使え!」
- 中島岳志の「希望は商店街!」
- 伊藤真の「けんぽう手習い塾」リターンズ
- B級記者、どん・わんたろう
- 伊勢崎賢治の平和構築ゼミ
- 雨宮処凛がゆく!
- 松本哉の「のびのび大作戦」
- 鈴木邦男の「愛国問答」
- 柴田鉄治のメディア時評
- 岡留安則の『癒しの島・沖縄の深層』
- 畠山理仁の「永田町記者会見日記」
- 時々お散歩日記
- キム・ソンハの「パンにハムをはさむニダ」
- kanataの「コスタリカ通信」
- 森永卓郎の戦争と平和講座
- 40歳からの機動戦士ガンダム
- 「沖縄」に訊く
- この人に聞きたい
- ぼくらのリアル★ピース
- マガ9対談
- 世界から見たニッポン
- マガ9スポーツコラム
- マガ9レビュー
- みんなのレポート
- みんなのこえ
- マガ9アーカイブス